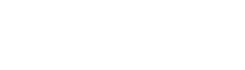作品詳細

忘れ潮
秘密がもう秘密でないのは/秘密を忘れてしまっただけの事さ
前略……各篇には幻想的な光景が織り込まれるが、現実と有限な世界のあわいは、淡くぼやけたものではなく、地続きに、また空や海を通して繋がり合った、実線で描かれた輪郭を持つようなありありとした景と映る。語彙や比喩の豊かさ、筆致の確かさが、微細な心の揺れと心情を感傷に溺れぬ強さで伝え、読者を引き寄せ共感させる。
(日和聡子 2021年11月6日東京新聞 詩の風景より)
海岸駅
小さな雨粒くぐってきた
大きな雨粒のように
うっすら汗をかいている
青白い星の
すこし開いた二階窓から
猫より薄い目となって
眺める沖の白波数しれず
普通の人が代を重ねる
どこにでもある日の出町の運河へ
夏潮とともに漂い出た
中身のない手袋が指さす方へ
肩傾けて歩みゆく
晴れぐもる六月空のような
分厚い少年の腫れ目
どこへ去っていくのだったか
どこから戻ってきたのだったか
向こう側でもこちら側でもあり
どちらの側でもない
赤い橋の途中で考える
どちらの側を向いても後ろから
聞こえてくる鐘の音
あれはなんの立て札だったか
赤かったり青かったりする
迷彩色の半島のような
水兵の腕のタトゥーのような
「新しい天と新しい地
最初の天と最初の地は去っていき
もはや海もなくなった」と
横に小さなベンチも置かれていたが
「座ることはできないよ」と
よそ行きの紅引いて
濃く甘い磯の匂いする
どこにでもある日の出町の
海岸駅にバス待っている
いつまでも石のように変わらない
姉さんのところへ帰りたい
無用の鍵
扉の向こうがまた扉なら
また鍵穴を探せばいい
だが開いた扉の向こう側が
鏡に映したように
寂しい鉄骨と停車場と空の雲の
こちらの町と同じだったらどうしよう
首を傾げる一行のような
扉に深淵があるとは言えない
思わず肯く一節なら
ただの砂糖菓子かもしれない
開かない扉は開かない扉
鍵などかざしてはいけないと
扉は言っているのかもしれない
扉を無理に開けてはいけない
意味の煙でくもらせてはいけない
夕まぐれの鳴かぬ鴉の夢に出る
叫びつつ坂駆け下りてゆく人になるな
きみ自身ただ草むらに捨てられた
無用の鍵かもしれないが
それでいいじゃないか
頭痛を忘れるほど
深々と眠り眩しい夢に眼を瞠れ
もし頭痛の名残のように
一筋の縒れ糸が眼の端に垂れてきても
それを信じてはいけない
その縒れ糸の向こうの海べりの
冬波に洗われる石くれ一つこそ信じよ
その糸に繋がったときは切れている
切れているときにこそ
あの空にも海にも繋がっている
空には相変わらず翼ある雲の馬
遠い国の歌のような海の音が聞こえる
鉄骨の影落ちる小さな停車場に
バスも旅人ももう見えなかった
拾った鍵は草むらに返し
この町は鳶と海へ返すときだ
冬帽子を目深に被りなおし
少年も歩み去る
詩集
2021/09/16発行
四六版
上製 カバー 帯付
装幀:木佐塔一郎