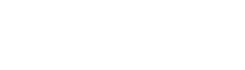作品詳細

散文の連なりについて
ずっと。人を思っている。雨が光を帯びはじめている。
これが小説なのだとしたら、時代への完全なる抵抗だと思う。
ファストな時代のファストな読書への回答として。
人生はカタルシスのための物語ではないことの表明として。
そして、詩的なるものへの復権として。
――梅﨑実奈
髙塚謙太郎『散文の連なりについて』は詩だ。
散文の連なりではあるものの、詩の水がひとしずく滴り落ち、やがてしとしとと連なっていくように、ここにある言葉ははじまり、つづいていく。
髙塚謙太郎の行分け詩は、語りの構造が裁断され細分化、複数化され緻密に再構成されていく極めて高度な書法に到達したが、ここの歩みは水の滴りのようにしとしとと進みやがて読者を詩の歩み、詩の呼吸そのものに同化させていく。
いつまでも。詩に終わりはない。
――朝吹亮二
詩とは韻律だ。では散文は?
髙塚謙太郎は、ありふれた物語も愛も信じてはいない。信じるのは、書くという情熱と虚無とともに流れる言葉だけだ。
雨や光や人や文字に初めて触れ、離れて思うようなこまやかさと緩やかさで言葉はたゆたい、流れ、記されたどの瞬間も互いに似ていない個別の愛しさとなり瞬く。やがて日常の方がこの言葉の瞬きを写し、生き直すだろう。
比類ない詩の書き手による、散文という時間との本気の戯れ。その連なりは切ないほどに美しい。
――峯澤典子
そういえば机上の時計が動かなくなって久しい。電池は、どこかにあったかな。それでも時針や秒針がいつかの時を刻んだ瞬間のままだということに、私は新たに驚いてもよかっただろう。そしてたぶん、そのときの私は時計の前にはいなかった。私だけがその瞬間を生きていないような、逆説的だけれど、そのくらい愛しい時間というものの深さを喩として書いていることが多いように思う。その証拠のように動きやめた時計だとしたら、この部屋はそれだけで完璧ではないか。
(本書より)
小説
2025/12/01発行
四六判
仮フランス装 小口折り 天アンカット