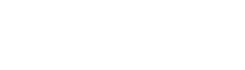作品詳細

光る背骨
たとえ撃たれて焼かれても/雨よ貫けわたしの骨を
十七世紀から二十世紀にかけて実在した五人の女性をテーマとした作品を収録する詩集。
マリア・シビラ・メ―リアン(ドイツの画家で生物学者)
高橋お伝(「毒婦」として伝説化された)
フリーダ・カロ(メキシコの画家)
メアリー・アニング(イギリスの古生物学者)
伊藤野枝(女性解放運動家でアナーキスト)
彼女たちの生きた時代や境遇を綿密に研究し、創造やイメージを働かせ、詩はつづられてゆく。
物事へ向き合う中軸とは何か。
著者はバックボーン、「背骨」をその作品の中に明確に浮き立たせている。
とりわけ伊藤野枝への作品は著者に野枝が憑依しているかのような迫力がある。
「雨よ貫けわたしの骨を」「「大杉栄へ――そのときあなたはもっと生きる」そしてラストの作品「誰も知らないまっくらな小道を通って」と続く。
書き終えた浦歌無子は体中をめぐる熱い血潮をどうやって収めたのだろうか。
「マリア・シビラ・メーリアン」より
メタモルフォーゼ
わたしが蛾になる前の
幼虫だったころ
冷たい夜露をすすると
夜がふかぶかとからだじゅうに染みていった
苦くて甘い葉っぱを食んで空いた穴から見える
朝のひかりが好きだった
サナギになったわたしに
葉っぱはあたたかなゆりかごとなり
さやさやと子守り歌までうたってくれた
一秒後には人間の子どもの手がやってくるかもしれない
おなかをすかせたムクドリに見つかるかもしれない
いつ強い風が吹いてくるかわからない
でもなにもこわくはなかった
生まれた瞬間から死がはじまることを
とっくに知っているのだもの
わたしはこんこんと夢を見ながら
溶けてなくなってゆく心地よさに恍惚となり
つくられ変化してゆく痛みとともに
時間を自由に旅していた
さかのぼったり超えたり
誰にも届かないところへと
そのあいだ外がわでは規則正しく夜が訪れていて
眠りから覚めたとき
瞳に訪れたひかりは
はじめてのひかりのようでもあり
何万回も見たひかりのうようでもあった
はるか遠いところから届けられたひかりが
わたしのひらききっていない生まれたての翅に
降りそそいでいた
あのひかりを忘れるな
たとえはじまりが終わりになっても
こわくはない
わたしはわたしを越えて
何億回も朝を迎える
「メアリー・アニング」より
骨の奥で開いてゆくのは
波打ち際に絡まっている
これは藻ですか
海の花ですか
それとも髪の毛でしょうか
岸を歩く
波の音
風の音
砂の音
もっともっとわたしは聴きたい
たとえばクラゲの鼓動
プランクトンの分裂
プレシオサウルスの咆哮
メアリー・アニングの足音
いつか深く深く聴くことができる日が来たら
そのときは歩ける
空を
海を
肺のことなど気にせずに
自分がこのままここで死んで
砂に埋もれて
肉が朽ちて
骨だけになって
水が満ちて
あたりいったい海になって
もういちど干上がって
遠いさき人類が絶滅したあと
なにものかに発掘されるかもしれないことを思う
(骨の形状よりホモ・サピエンスであると思われる
全長一六〇㎝
目立った特徴なし)
緑いろの蛾を見つけるたびに見とれること
ときどき石を拾うこと
片づけをいつも途中で投げだしてしまうこと
バニラアイスを毎日食べること
足の速い蜘蛛がこわいこと
メニューがなかなか決められないこと
雨の音と匂いにぼうっとすること
もう誰も履かない靴をいつまでも捨てられないこと
紅茶を濃く入れすぎてしまうこと
文鳥の風切羽をお守りにしていること
伝えそこなった言葉があることを思いだしては悔やんでいること
言い合いの果てもう一歩も動けないと思った日があったこと
言い間違いがおかしくて笑いがとまらなくなった日があったこと
わたしはいつか
骨だけになる
誰にも見せたことのない白い骨
海からどんなに遠ざかっても
骨には海が沁み込んでいる
骨ばかりになっても
誰かを恋しがって
わたしの海は鳴くのだろう
✿ 2022年8月6日発行の図書新聞に、皆川勤さんによる『光る背骨』の書評が掲載されました。
詩集
2021/11/12発行
A5判変形 (140x200)
上製 カバー帯付
装幀:毛利一枝