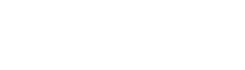作品詳細
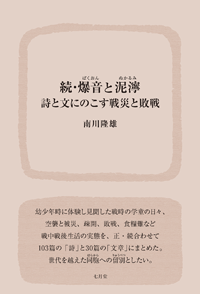
続・爆音と泥濘
詩と文にのこす戦災と敗戦
詩と文に残す戦災と敗戦
幼少年時に体験し見聞した戦時の日々。空襲と被災、疎開、敗戦、食糧難など戦中戦後生活の実態は歴史書はいうに及ばず年表や年鑑からはけっして読みとれまい。それをいまのうちに「詩」と「文章」に書き遺した。世代を越えた同胞への留別としたい。
橋
中空からながめていると
老爺になり果てたわたしが
右手から橋の半ばまで足を引きずってきて
欄干にもたれかかり 反った板塔婆(いたとうば)になった
水面になにを見ようとしているのだろう
やわらかな手に導かれてあの未明
この橋を生きる側に逃げ渡ったのだった
土手のひがん花ほどに鮮やかな光景
グラマン・ヘルキャットの操縦士は余裕綽々
低空での曲芸をたのしんでいたらしい
もも色の顔 高い鼻をみた マフラーをしていた
そんな話ができたのは十年も後のこと
夜明け 目隠しされた指のすきまから見たものは
かわり果てたわか町わが姿
にんげんの所業がまとめて燃えつきるにおいは
じぶんの皮膚の綻(ほころ)びからも燻(いぶ)り出ていた
禍々しい舞台にたたずみ
わたしの手を引くいとおしいたましい
おかげでわたしはじゅうぶんに生きおおせた
ひとに聞いてもらいたいことも もう尽きた
川砂を這う線香のけむり
ながめていると 板塔婆がさらに反る
欄干を跳ね出るいきおいで
伊賀上野への旅
(前略)目の前にいるこの家の老主人はかつて父の戦友だったと聞いている。しわを刻んだ日焼けした顔のなかの二つのくぼみから柔らかな細い目が私に注がれている。見かけは亡父よりもいくらか年配に見える。私と同年くらいのその家の息子さんが奥から出てきた。伊賀上野は初めてですか、と問われたのをきっかけに、終戦の翌年に初めて伊賀上野を訪れたときのことを私はしぜんに思い返すことになった。
復員時に父が背嚢(はいのう)に入れて持ってきた書きもののなかに戦時名簿があり、所属部隊の移動の記録がごく簡素に記してあった。これによると父は敗戦後の拘留期間を経て昭和二十一年(一九四六)四月十六日に河南省の許昌を発ち、上海から出航して五月四日に紀伊の田辺に入港し、同日召集解除になっている。応召を見送られた町や自分の生家はもちちん空襲で焼けて跡形もなかったが、焼け跡でたまたま出遇った顔見知りの人に家族の疎開先をおしえられて、ようやく一家が合流したのだった。祖母、つまり父の母親が同年正月に病死していたものの、戦災のために一家で欠けた者はなく、父の復員もむしろ順調なほうであった。
その後の生活のことや祖母の納骨など早々にやらねばならないことがいろいろとあっただろうが、復員してきた父がまずしたことは、伊賀上野へ行くことだった。父にはその地の出身で最後まで行動をともにした戦友がいて、この人は復員を前に病気療養が必要になり、帰国が遅れることになった。遅れているのはこの人の身に特別のことが生じたわけではないので、体調が回復し次第まちがいなく帰国する、とただそのことを留守家族にじかに伝えるのがこの日帰りの旅の目的だった。そんなことを後になって私は聞かされた。もっとも家族連れ立っての旅だったので、幾年ぶりかの慰安も兼ねていたのだろう。その人は、父の話したとおり数か月遅れて無事帰国したという。
伊賀上野は戦火を免れた。戦災に遭っていない町並みを見るのは気持ちがよかった。当時の木造の伊賀上野駅はそれでもその周辺では最も大きな建物だった。駅の構内には雑草が線路を覆うように生えていた。私たち家族は改札を出るとすぐに駅前の外食券食堂に入ったが、なぜか断られて食事にありつけなかったのを記憶している。そして、そのまま上野城へ向かった。父は私たち家族を城へ案内しておいて、すぐさまとって返し、戦友の留守宅へ行ったようである。
すでに夏に入っていた。城に近づくにつれて急に風がさらさらと鳴りはじめ、なぜかほっとした気分になった。母は庭石をみつけて終始そこに腰掛けたままでいた。私と弟も遠くへ行かずに母の目の届くあたりで遊んいたようである。そこはそり返った天守閣の石垣の真下だった。短い時間に思われたが、そのうちに歩幅いっぱいの歩きっぷりで父は戻ってきた。大きな茶色の編上靴が私の間近にあった。私たちはそれからまっすぐに駅へ戻り、そのまま帰りの汽車に乗った。私の最初の伊賀上野への旅はこれがすべてである。(後略)
既刊「爆音と泥濘」
詩文集
2020/01/20発行
四六判 (128x188)
並製 カバー付き