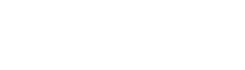作品詳細


うみのほね
己のうちに侵入した異物をやわらかい層で覆い結晶化するバロック真珠のように
この詩集のタイトルにもなっている「うみのほね」は散文で詩的小説である。
李という若者との生活を中心に描かれる自伝とも思えるような短編小説である。
(彼の虹彩は果てしなく暗い色をしていて、私の顔が写っている。その私の顔の中に彼の姿がまた映り、きっと永遠に続いているんだ。これは奇跡だ、そうじゃなかったらなんだろう。)
多くの場面の一つ一つは現実の惨い世界ではあるが、美しく豊かな情感にあふれている。
詩人白島真が跋で田中修子との出会いからその作品の全容を語っている。
「丸鏡の向こうのわが家」
うつくしい家にかえる
秋の赤みをおびた夕暮れ色のレンガをふむ
玄関にはアール・ヌーヴォー調の
金色のふちの大きな丸鏡にむかえられる
この丸鏡の前に花瓶をおき
庭に咲いた花を飾る
と、鏡の向こうの玄関にも花が咲く
(いまの季節なら手まり咲きの
まだ緑色のところがうっすら奥にのこっている
この株の大きくなりすぎた青い紫陽花
おとなりにはみ出してしまいそうな枝のを)
母と父 祖母 妹と兄
すべてのあこがれがこめられたこの家の
胸に閉ざした
秘密
この家はわたしの家ではない
あのころ見捨てられたわたしはいまもどこかで
やさしいほんとうの家族に見守られながら
眠りこけているだろう
夕暮れ色の煉瓦の階段から続くバルコニー
淡いきみどりのハナミズキの葉影に
おだやかに泳ぐ甕のめだかたち
白いドアをひらき
金色のアール・ヌーヴォー調の鏡
ただいま
詩集
2019/04/27発行
四六判変形
並製 カバー付
跋:白島真