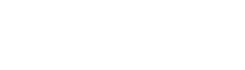作品詳細

公園のまんなかにはおおきな木があって
届かないものを あなたと分かち合いたい
たかすかさんの詩とともに散歩し、佇み、微かな風を肌で待ってみる。
それは果てしなく孤独で、自由で、色気のある時間だ。
――三宅唱(映画監督)
途上
坂の途上の地面は断層が剥き出しになっていて
茶色と灰色の入り混じった土が不安定に固められた足場を伝いながら
白いヘルメットを被り、紺色の作業着を着たひとがひとり降りてきて
奥の空間へと消えていく
奥では鉄骨と青いシートに覆われた穴だらけの家が
完成を待っているのか
解体を待っているのか
浅く削られた地面に鎮座していて
その横で風に揺れ斜めに伸びる一本の木の緑が
家の中を行き来する作業着たちの影を曖昧に拡散している
オーストラリアっていま何時だっけ?
風にのって不意に届くカタカナの地名が
坂に乗って不安定に傾くからだの姿勢をかたかたとなぞり
謎かけをたのしむように笑い声が遅れてやってくる
ひゃ、ひゃ、ひゃ、ひゃ、と
穴から風が漏れるような破裂音が辺りに響き
それにあわせるようにシャッター音が三度、
坂の上から鋭くたてつづけに鳴る
撃たれたように振り仰げば 空を覆う黒と灰の雲が
うすくれないに染まりはじめた眼下のまち並みと
層を成しながらゆっくり下降する
加工され固定された時間をカメラにおさめたそのひとは
鳥の囀るオーケストラを背後にしながら
この世の反対側にいるみたいな深く沈む眼差しを
剥き出したまま、途方に暮れて佇んでいるようにみえる
中央区立浜町公園
橋の向こうのまちのことはよく知らなかった。とぐろを巻く首都高が空を覆い、その真下の空き地で父親がちいさな子ども二人と遊んでいた。さらに進んで、大きな通りで右に曲がった。真っ直ぐ行くとまた別の橋があるらしかった。橋を渡ったらまた橋って、なんかどこにも行けんみたいやん? きっとあなたならそう言った。橋の手前で左に折れて、公園に寄った。公園では着物を模したお揃いの服を着た子ども四人がかくれんぼをしていた。隠れる場所はあまりなさそうだった。大人たちは水辺のベンチで談笑していた。その水辺に野生のネズミが一匹どこかから現れて、とてもおいしそうに水を飲んだ。公園内の照明はどれも濃い橙色だった。陽はまだ沈みきっていなかったけれど、もう空には陽が生み出す橙色は残っていなくって、陽が水平線に消え去る瞬間の淡い黄色だけが西の空にうっすら膜となって残っているだけだった。だから公園を満たす橙色は全部人工的なもので、人工的な橙色を透かして見る人間たちは、どれも古い映像のなかのひとたちみたいで、なんだか過去のようだった。もちろんそこにあなたはいなくて、わたしはひどく安心し、安心したことにひどく胸を痛めた。それから公園脇の階段から川沿いの遊歩道へ降りた。橙色は届かなくなり、陽はすっかり沈み、一段一段降りるごとに辺りは暗くなっていった。川は巨大で、真っ黒い水はひどく波打ち、歩道まで溢れてきそうだった。怖かった。そう思っていたら呑み込まれた。
それは言い訳でしかないんやん? きっとあなたならそう言った。良いわけがない。良いわけがない。意味なくくりかえすわたしはまだ川沿いの遊歩道を歩いていた。わたしのからだを運ぶのはわたしの足だった。しらじらとした蛍光灯の明かりにまみれたわたしの足の足裏が、地面に着地するまでの時間とその隔たりを正確に測る必要があると思った。目の前には色とりどりのネオンにライトアップされた大きな橋があり、川面にネオンがモザイク状に映って揺れていた。川を遡る一艘の船が橋の下を垂直に通過し、船が通った跡で切断されたネオンが揺れていた。石を投げればネオン色の煙が上がるだろう。煙の中からあなたが現れるだろう。けれども石はなかった。いつまでもアスファルトの平らな道だった。橋の上から車のヘッドライトが鋭くこちらを射す。隠れる場所はなかった。
詩集
2024/08/04発行
A5判変形 (140x210)
並製 カバー 帯
表紙絵:パウル・クレー「花ひらく木をめぐる抽象」東京国立近代美術館蔵 Photo:MOMAT / DNPartcom / 帯文:三宅唱(映画監督)