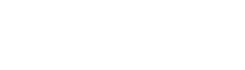作品詳細

子犬は跳ねて 空の色に溶けた
生きる神秘 そのアイロニーを超えて
私たちは不確かな日常を生きている。
私たちはヨブの日々を生きているのかもしれない。
「受難という永劫の受動態を、一瞬だけ受動態に置換するモメント、それが詩である」野村喜和夫の栞文より
「紫陽花の森」
ベッドに腰掛け、テレビの画面を眺めていた母
「ひさしぶり わたし 誰だかわかる?」
目をあわせずに、窓の外に視線を移す小さな背中
介護療養病棟の真四角な天井に
無言の時間が流れる
「散歩 行こうか?」
杖を片手に立ち上がった母が着ていたのは
袖口がほつれたTシャツ
父があわてて選んだのだろう
私は着ていたレモン色のカーディガンを脱いで
そっと肩にかける
「あめ ふってないのね」
つぶやきながら母は、曇り空を見上げる
裏庭へ回ると、小道の脇に幽かな光を放つ一群れ
紫陽花だ
母の顔がぱっと輝き
私の手をひいて転がるように近寄った
レモン色に背中を丸め
色褪せた花に頬をよせて、いつまでも眺めている
(知らなかったよ 好きだったんだね あじさい)
散歩から戻り、ベッドへ倒れこむと
花を眺めていたときの横顔で
小さな寝息をたてた
帰りのバスの後部座席
振り返ると、紫陽花がこんもり茂った一角
戯れながら折り重なる花々が、森のように咲き誇り
建物の白壁を鮮やかな群青色に覆い隠している
(守られていたんだね 花たちに)
ガラス窓の向こう
冴え冴えと浮き立った紫陽花の森が
曇天の空まで 広がっていて
「きみはいつも」
けっこんしようか
こいぬのみみもとに
ささやいた
けっこんってなあに
てれびをみながら
こいぬがたずねた
いつまでも
いっしょにいようねって
おやくそくすることだよ
わたしのひざのうえに
あごをのせたまま
こいぬはちいさく
あくびをした
* *
きょうはこれがいいな
こいぬがせのびして
コンビニのたなから
トマトジュースをえらぶ
かいものかごいっぱいに
ビールとぽてちもほおりこむ
レジにならんで
小銭をかぞえるわたし
ガラスとびらのむこうで
そらをみあげるきみ
きづいてたよ
きみはいつも
ざわわ
ざざざわ
かぜのおと さわがしいから
ゆうぐれのさんぽは
ここまで
詩集
2022/09/27発行
四六判
並製 小口折り 栞付き